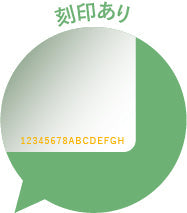ICカードにまつわるお役立ち情報
ICカードのセキュリティとは?FeliCa・MIFAREの仕組みと安全性を徹底解説

ICカードのセキュリティとは?仕組みと安全性をわかりやすく解説
近年、社員証や勤怠管理、入退室管理、電子マネーなど、ICカードは私たちの生活やビジネスに欠かせない存在となっています。 しかし、その便利さの裏には「セキュリティリスク」も潜んでいます。本記事では、ICカードのセキュリティの仕組みや脅威、そして安全に運用するためのポイントについて解説します。
ICカードの基本構造と認証方式
ICカードは、内部にICチップを搭載し、暗号化されたデータをやり取りすることで認証を行います。 主に「非接触型ICカード(RFID方式)」が使われており、カードリーダーにかざすだけで通信が可能です。 認証方式は大きく分けて以下の3種類があります。
- UID(IDm)認証:カード固有の識別番号を照合する方式。簡易的で導入しやすいが、セキュリティは低め。
- セクター認証:特定の領域にアクセスキーを設定し、暗号化通信を行う方式。
- 相互認証:カードとリーダー双方が暗号化キーを使い認証し合う高セキュリティ方式。
代表的なICカードのセキュリティ比較
日本で多く使われるICカードとして、「FeliCa」と「MIFARE」があります。 両者とも暗号化技術を採用していますが、設計思想や方式に違いがあります。
| 項目 | FeliCa | MIFARE |
|---|---|---|
| 暗号化方式 | 独自方式(ソニー開発) | Crypto1 / AES方式 |
| セキュリティレベル | 非常に高い | 製品により異なる(MIFARE Classicは脆弱性あり) |
| 採用分野 | 交通系・社員証・電子マネー | 学生証・入退室・会員証など |
ICカードのセキュリティリスク
セキュリティ技術が進化しても、運用面でのリスクは常に存在します。代表的なリスクは次の通りです。
- カードの紛失や盗難による不正使用
- 複製・クローンカードの作成
- 通信の傍受やリーダー偽装
- アクセス制御設定の誤りによる情報漏洩
安全にICカードを運用するためのポイント
ICカードのセキュリティを最大限に活かすには、技術的な対策だけでなく運用管理も重要です。
- UID認証のみの運用は避ける:必ず暗号化や相互認証を採用する。
- アクセスキーを定期的に変更:長期利用による漏洩リスクを軽減。
- カードの管理体制を整備:発行・廃棄・再発行のプロセスを明確に。
- セキュリティチップを選ぶ:FeliCa Lite-SやMIFARE DESFireなど、安全性の高い製品を選定。
まとめ
ICカードは便利で効率的なツールですが、その安全性は「仕組み+運用」で成り立ちます。 導入時にはカードの種類や認証方式を理解し、適切なセキュリティレベルを確保することが大切です。 安全なICカード運用は、企業の信頼と業務効率を守る第一歩となります。